「ながら勉強」はアリ?ナシ?効果的な活用法と注意点を徹底解説

「音楽を聴きながら勉強」「家事をしながら講義のリスニング」など、何かをしながら勉強する“ながら勉強”。
時間の有効活用にも思えますが、本当に効果があるのでしょうか?この記事では、ながら勉強のメリット・デメリット、効果的な活用法と注意点を、実体験も交えつつご紹介します。

ながら勉強とは?
ながら勉強とは、別の作業や行動を同時に行いながら勉強するスタイルのことです。
たとえば以下のようなものがあります:
- 音楽を聞きながら問題集を解く
- 通勤中に英語のリスニングをする
- 掃除しながらYouTubeで講義を流す
ながら勉強のメリット
① 時間の有効活用ができる
忙しい社会人にとって、スキマ時間の活用は重要です。通勤や家事の時間を使えば、勉強時間を“新たに確保する”必要がありません。
② 気軽に取り組める
「机に向かって勉強するのは気が重い」という人も、ながら勉強なら心理的ハードルが下がり、取り組みやすくなります。
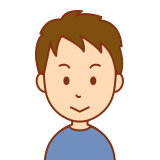
ながら勉強の最大のメリットとも言えますね!
③ 習慣化しやすい
毎朝の支度や通勤に勉強を組み込むことで、自然と「学びの習慣」が作られます。

ながら勉強のデメリット・注意点
① 集中力が分散する
特に「考える系の学習(例:数学の問題演習や暗記)」は、集中力が必要です。音楽や他の動作があると、効率が落ちることがあります。
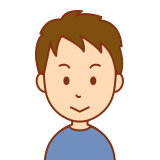
難問を解くには、ながらでは難しいですよね…
② 記憶に残りにくい
意識が分散すると、内容が頭に入りにくくなります。インプットより“ながら”はアウトプット系の勉強に向いているかもしれません。
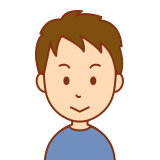
コツは今のは「こういうことかな?」と頭で考えると記憶に定着しやすくなりますよ!
③ 意味のない“ながら”になりやすい
流し聞きで「勉強してる気になる」ことも。学習内容に意識が向いていないと、時間だけ消費することになります。

効果的な「ながら勉強」の活用法
① リスニングや復習中心に使う
「ながら勉強」は、すでに学んだ内容の復習や、リスニングに特に効果的。英語や資格講座の音声を繰り返し聞くのがおすすめです。
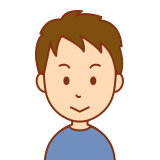
あくまで復習するくらいの感覚で取り入れると効果的ですよ!
② 作業との相性を考える
身体を使う単純作業(洗い物・ジョギングなど)と組み合わせるのがベストです。考える作業(仕事の資料作成)と同時並行は避けましょう。
③ 意識的に“聞く・考える”時間も作る
ぼーっと流すだけにならないよう、5〜10分でも「集中して聞く」時間を設けると理解度が深まります。
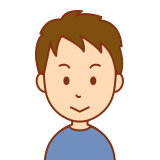
ここは覚えておきたいところを優先順位を決めておきましょう!

実際にやってみた!僕の「ながら勉強」体験談
筆者もFPの勉強をしていた頃、家事や通勤時間に「講義の音声」を聞いていました。最初は聞き流しでも、何度も同じ内容を聞くことで、自然と内容が定着していく感覚がありました。
ただし、机に向かって「問題を解く」時間もセットでとっていたので、ながらだけに頼らないのがポイントです。
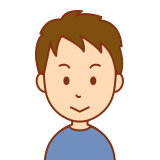
ながらは全体像の把握程度で!!

まとめ|ながら勉強は“使い方次第”で効果あり!
ながら勉強にはメリットもデメリットもあります。大切なのは、「どんな内容を、どんな状況でやるか」を意識すること。
- ✔ リスニングや復習に向いている
- ✔ 集中力が必要な作業は避ける
- ✔ スキマ時間の学習におすすめ
「ちゃんと勉強しなきゃ」と気負わず、まずは生活の中に“ながら勉強”を取り入れてみるのも一つの手です。
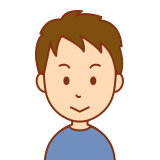
義務感でやってしまうと効果半減…楽しむのを意識してみて頑張りましょう!
あわせて読みたい
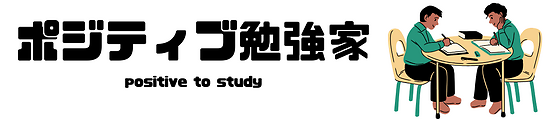
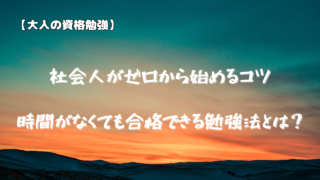
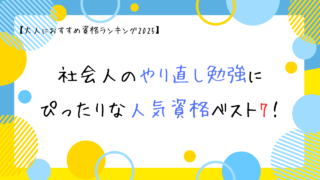
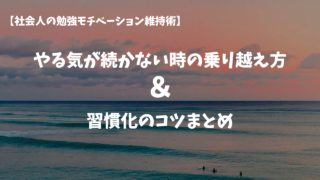
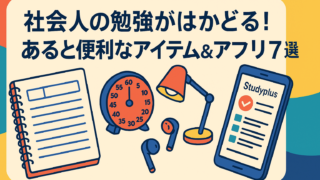
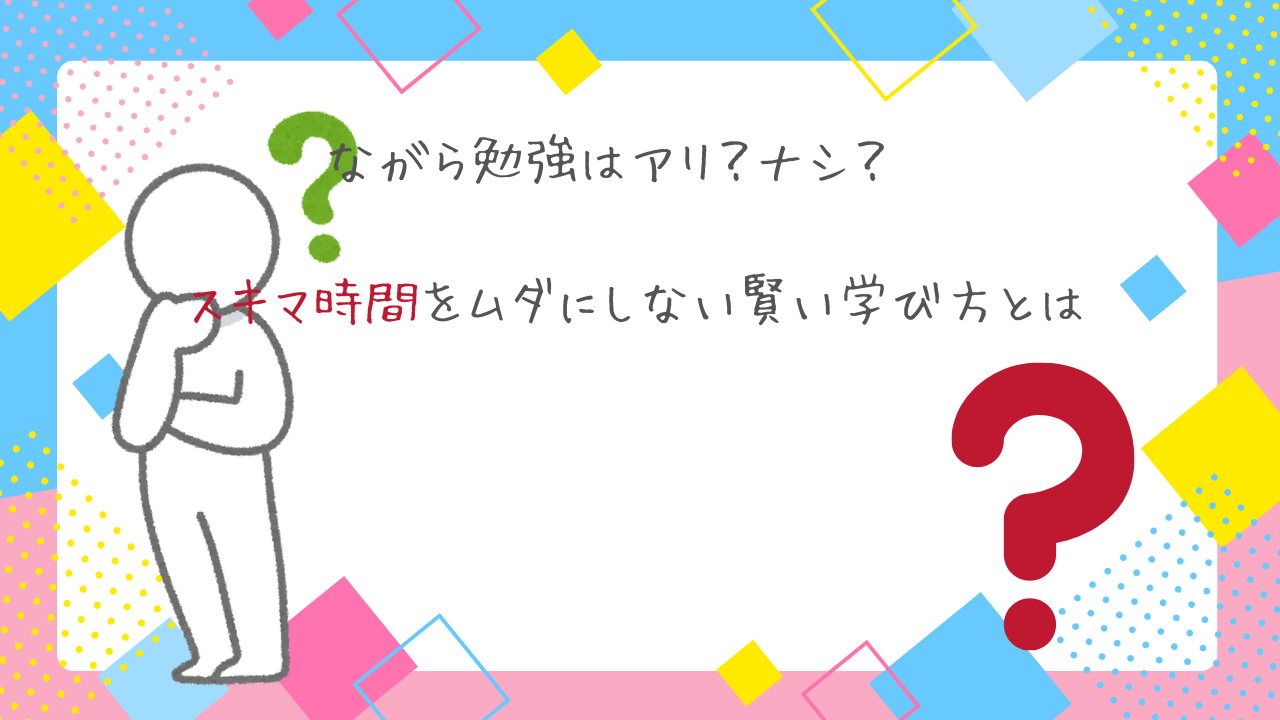
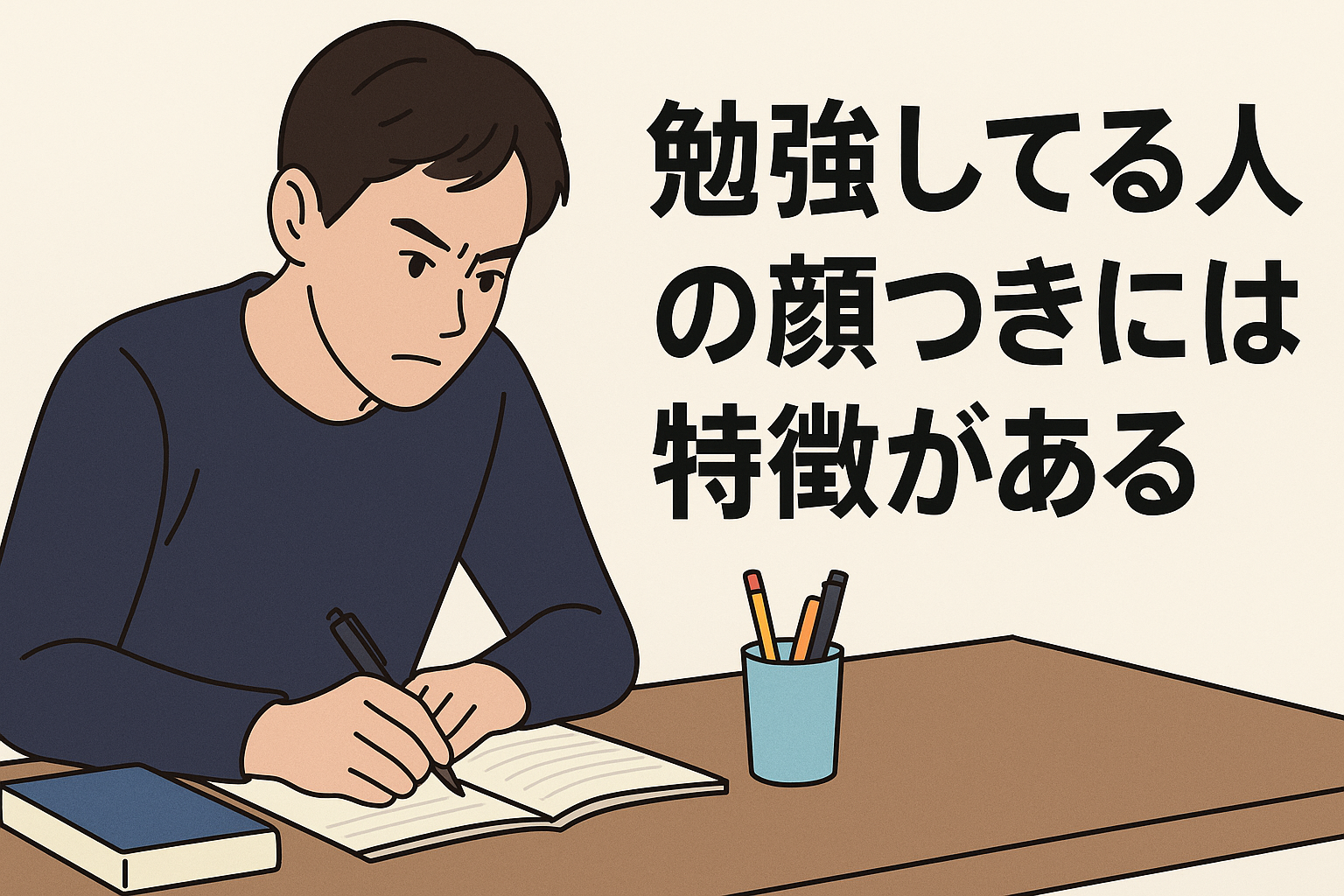


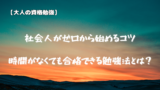

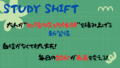
コメント