日商簿記3級ってどんな資格?社会人に人気の理由とは?

日商簿記3級ってどんな資格?社会人に人気の理由とは?
🔸 簿記3級は「お金の流れ」がわかるようになる資格
日商簿記3級は、簿記の基本的な仕組みを学ぶ入門資格です。企業のお金の流れや帳簿の付け方を理解するのに役立ち、特に事務職や経理補助の業務に興味がある方にとって、良い学習きっかけとなります。
資格そのものが直接「転職に有利」「給料アップ」と断言することはできませんが、「会計の基礎を知っている」という安心感が得られるのは、社会人にとって大きなメリットです。
🔸 僕が簿記3級を学ぼうと思った理由
筆者自身も「家計管理をもう少しきちんとしたい」という気持ちから簿記の学習を始めました。数字が苦手な自分にとってはチャレンジでしたが、「収入・支出の仕組み」がわかるようになったことで、普段の生活でも考え方が少しずつ変わっていきました。
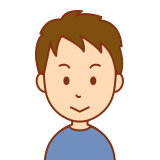
会計、経理などの転職する際に3級があるとアピールができますよ!
人気資格ランキングも作成しているのでよろしければ是非読んでみてくださいね↓

簿記3級と2級の違い|どっちから受けるべき?
| 比較項目 | 簿記3級 | 簿記2級 |
|---|---|---|
| 難易度 | ★☆☆ | ★★☆〜★★★ |
| 合格率 | 約40〜50% | 約20〜30% |
| 内容 | 小規模な個人商店レベル | 中小企業・企業会計レベル |
| 学習時間の目安 | 60〜100時間 | 150〜300時間 |
📌 初心者はまず3級からスタートが鉄則!
特に商業高校出身でもない限り、いきなり2級は挫折リスク大です。2級をいきなり受ける方でも3級の勉強を行い、基礎を固めてから受けるのが良いですよ!

日商簿記3級の勉強法|未経験からでも安心のステップ
🔸 ステップ1:まずは公式テキストでざっくり全体像を把握
簿記の世界では、最初に「全体像」をつかむことが大切です。おすすめなのは、日商簿記公式サイトが紹介している範囲をもとに構成されたテキスト。具体的な例や図解があるものを選ぶと、数字が苦手でもとっつきやすくなります。
🔸 ステップ2:インプットとアウトプットをバランスよく
例えば、筆者は以下のような方法で学習していました:
-
平日は1日30分だけテキストを読む
-
週末に過去問や練習問題を解く
-
スマホアプリを活用して移動時間にも復習
市販の過去問題集を数冊こなすと、「あ、これは見たことある!」という感覚が身についてきます。
ぼくが使用した教材を貼ってますのでよろしければ是非検討してくださいね↓
🔸 ステップ3:モチベーション維持は「小さな目標設定」がコツ
「2ヶ月で取る!」と大きく構えすぎると逆に続かないことも。
「今日は2ページ読む」「1問だけ解く」など、毎日少しずつの積み重ねが成功の秘訣です。スケジュール帳や学習アプリで進捗を可視化するのもおすすめです。

社会人でも続けられる!簿記学習の時間の作り方
「忙しくて時間がない…」という社会人でも、1日30分の積み重ねで合格圏内です!
🔄 勉強時間の工夫ポイント
-
朝活で20分だけテキスト読み
-
通勤中にアプリで問題演習
-
夜は動画で復習(ながら視聴OK)
「完璧主義にならない」のが継続のコツ。疲れてる日は3問だけ解く!でもOKにしてました。

2級は次のステップ!受けるべきタイミングと勉強法
📌 2級に挑戦するベストタイミング
-
3級に合格した勢いでそのまま!
-
実務に近い内容なので、経理系・経営職を目指す人に特におすすめ
勉強法の違い
2級では「工業簿記」が登場し、計算や記述問題が増えます。
問題演習の量が鍵になるので、2級は通信講座や模試中心の勉強もアリ!
僕はLEC東京リーガルマインドをよく使用しておりました!資料請求は無料なので是非検討してくださいね↓
✅ まとめ:簿記はビジネスの基礎力アップに直結!
-
簿記3級は初心者に優しく、2〜3ヶ月で合格できる国家資格
-
働きながらでも「通勤中+朝夜30分」でスキマ勉強可能
-
簿記2級まで取れば、転職市場でも一目置かれる存在に!
日商簿記3級は、仕事だけでなく日常生活でも活かせる「お金の教養」を学べる資格です。未経験からでも、基礎テキストやアプリ、過去問を活用すれば、理解を深めながらコツコツ進めることができます。
「経理職じゃないけど取ってよかった!」と感じる人が多い資格です。
まずは3級から、気軽にチャレンジしてみてください!
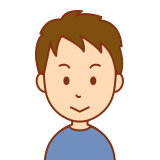
自分のキャリアアップのためにも頑張っていきましょう!
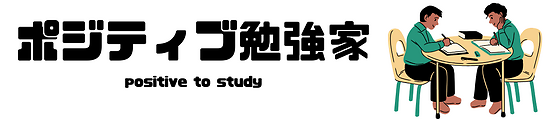
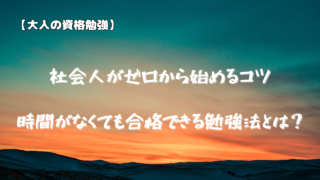
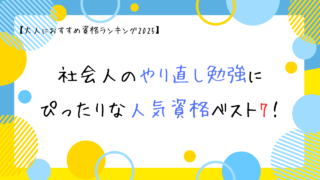
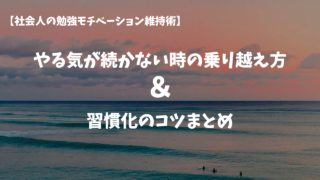
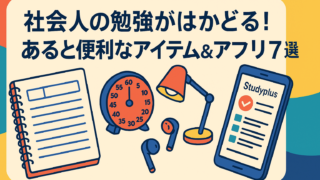
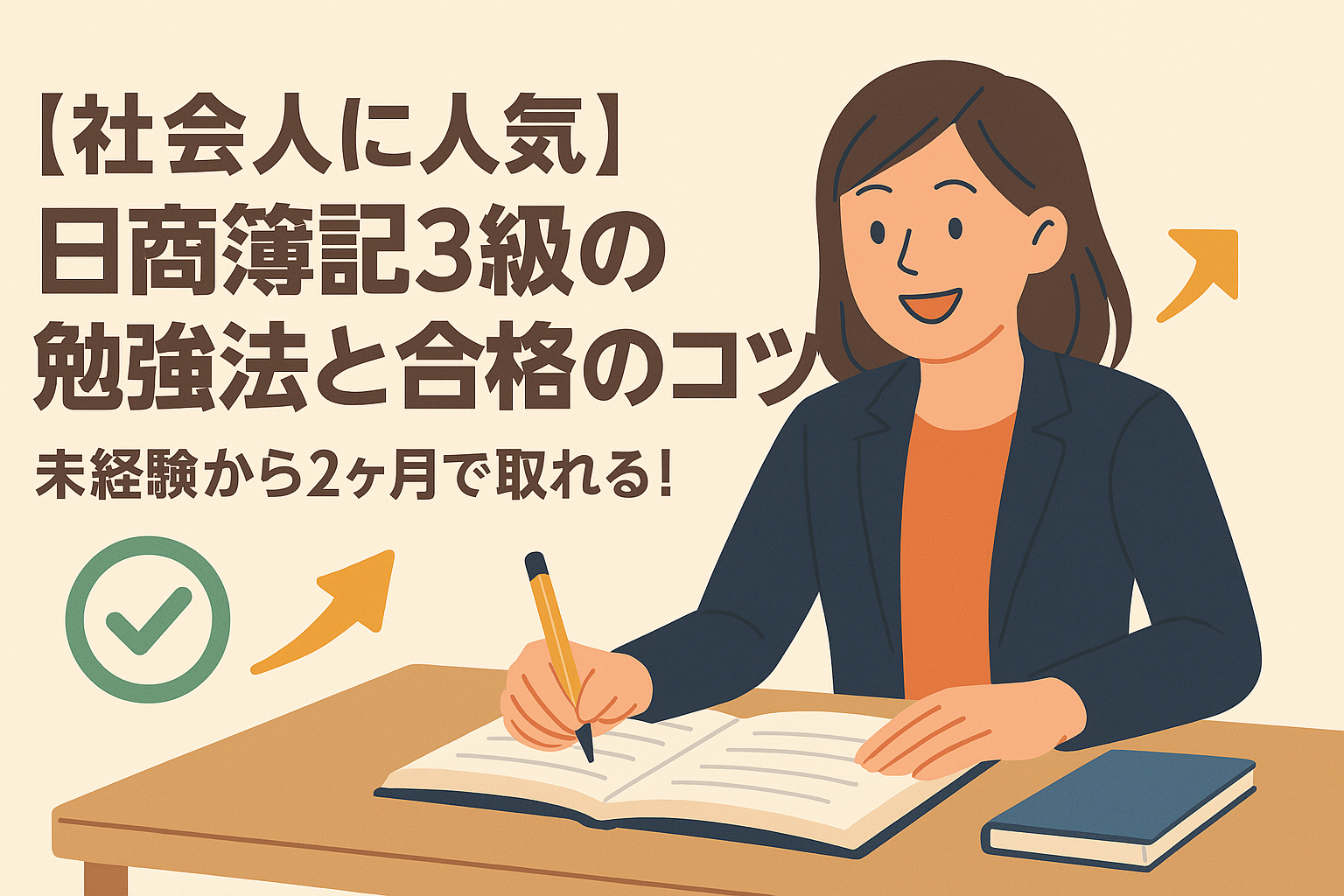


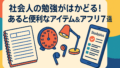
コメント